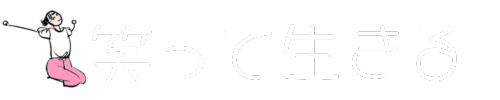駄菓子屋に毎日通っていた
おーばーちゃん、10円で!
まるで歌うように節をつけてそのお店の入り口でおばちゃんに声を掛ける。それがその界隈の子供達のお約束でした。
入ったらそこは夢の世界でした。狭さと薄暗さが相まってドリーム感を増していたような気がします。
ここに来れば何でもある、と思っていたと思います。
昭和43年。
私は小学1年生。妹は当時2才。
小さな妹は「おばちゃん、10円で!」が言えなくて「おば、じゅう!」と省略。
大きな声を張り上げていました。
「おば、じゅう!」って今思い出しても可愛いです。
あの時代を私は本当に過ごしていたのか、作り上げられた記憶なんじゃ無いか。
なんて事を考える時もあります。
ALWAYS 三丁目の夕日の世界そのままでした。
このお店の名前は『おぎた商店』(たぶん)
店にいるおばちゃんを子供達は『おぎたのおばちゃん』と呼んでいました。
うっすらな記憶しか無いですが恰幅のいい女性だったと思います。いつも割烹着だったような。
これも作られた記憶なのか。今となってはわかりません。
でもあの頃の事が私の頭の中に確かに存在しています。
いつでもあの頃の匂いを感じる事が出来ます。
怒るとこわい おぎたのおばちゃん
ある日、おばちゃんの店を前を通りかかると小学生(たぶん3年生か4年生位)が数人、店の前で立たされていました。みんな泣いています。
おぎたのおばちゃんの店は小学校の向いにありました。まだ道も舗装されて無い、車がやっと通れる位の砂利道をはさんだ向かい側が小学校でした。
その小学校のブロック塀を背に立たされていたのです。
聞くところによると(誰に聞いたのか?)立たされている子供達はおばちゃんのお店で万引きをした、との事でした。
しばらく様子を見ているとおばちゃんが中から出て来ました。
子供達の前まで行って鬼の形相で何か言っています。
2度とするんじゃないよ。位の事は言ってたと思います。
あまりにおばちゃんが怖くてその場を立ち去ったので、子供達はその後解放されたのかは不明です。
優しいと思っていたおぎたのおばちゃん。見る目がその日から変わりました。
怒らせてはいけない。と子供心に誓った事でしょう。
ある日環境が激変した
父の商売が上手く行って小金を稼いだのか、大阪の下町から高級住宅地へ引っ越す事になりました。
1年生の2学期ごろだったと思います。これが私の転校の最初です。この後、転校を繰り返すのはまだ後の話。
大阪の下町は情緒にあふれていました。
夏の夜。家の外に縁台を出してステテコ姿のお父さん達が将棋を指していました。
町はドブ川のような匂いがしていたと思います。でもそれが好きだった。
途中で家にお風呂ができましたがそれまでは銭湯に通っていました。
お風呂上りに買ってもらうフルーツ牛乳が最高のごちそうでした。
あのクリームががったオレンジ色と甘ったるい味。今でもフルーツ牛乳大好きです。
今でも大阪の下町を歩くと、とてつも無く懐かしい気分になります。
やっぱりそこではドブ川の匂いがします。
高級住宅地ではその全てが無かったです。
大体駄菓子屋さんが無い。
みんな家でお母さんが作る手作りのおやつを食べるのです。
隣のお家に遊びに行った時に出してもらった「イチゴ牛乳」
イチゴにお砂糖かけて牛乳かけて、潰して食べる。
こんなおやつを食べたのは初めてでした。衝撃でした。
美味しいと思ったのか「なんじゃこれ?」と思ったのか今となっては覚えていません。
お母さん達はみんな家に居てお庭でお花の世話をしたりしています。絵に描いたような世界です。
私の家も庭に花壇と小さな畑、そして小さな山がありました。
山は造園の業者さんに作ってもらったのでしょう。山と呼ぶには小さすぎますが木も沢山植えられていて子供がひとり探検出来る位の大きさがあります。
ちょっとしたワクワクスポットでした。
あの家の事を思い出すとき、どこからか金木犀の香りが漂ってくる錯覚に陥ります。
花壇と畑と小山。あとは芝生が植えられ、子供用の滑り台が置いてありました。
日本の高度成長期ですね。父の一番ノリノリだった時期かも知れません。
子供なので家が金持ちになったと言う認識は全くありません。嬉しくともなんとも無かったと思います。
おぎたのおばちゃんの所に行けなくなった。あのドブ川の匂いがしなくなった。
子供は変わりゆく環境をただ受け入れるしかありません。
そしてこの生活も終わりを告げる時が来るのはこの時の父も母も知りません。
それから起こる事を知る私はその時代を思い出すとき、懐かしいと言うより少しばかり胸が苦しくなります。